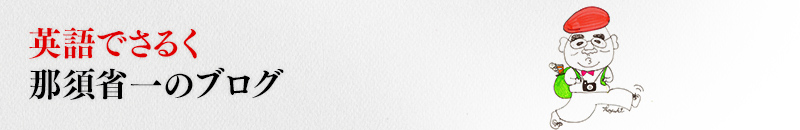- 2018-10-23 (Tue) 11:13
- 総合
 催眠剤代わりの書物を探そうとしていたら、恰好のものを見つけた。お世話になっている出版社が海外の作家を招いた読書会を月末に計画しており、参加を誘われた。招かれた作家はチベットの作家。それなら作品の一つぐらいは読んでおくべと思ったからだ。
催眠剤代わりの書物を探そうとしていたら、恰好のものを見つけた。お世話になっている出版社が海外の作家を招いた読書会を月末に計画しており、参加を誘われた。招かれた作家はチベットの作家。それなら作品の一つぐらいは読んでおくべと思ったからだ。
作家の名前はラシャムジャ。奥書にlha byams rgyal というアルファベット表記もあるが、これがラシャムジャという発音となるとは到底想像できない。拉先加という簡体字表記も添えられている。1977年にチベット(中国青海省)に生まれ、北京の中央民族大学にてチベット学を修めた作家。チベット文学を代表する若手の注目株と紹介されている。2012年に刊行された長編小説『雪を待つ』(勉誠出版・星泉訳)を手にした。
「それはある雪の朝のことだった」という語り手(主人公)の幼児の頃の回想で始まる。主人公はマルナン村という寒村の村長の息子。訳者の解説によると、「一九八〇年代に著者が少年時代を過ごした故郷の様子が細部に至るまで細かく描写されている」。私は読んでいて自分自身の子供の頃を思い出すシーンが幾つかあった。例えば、村に初めてテレビがやってきたときの描写。村長は村一番のやり手だからテレビを最初に購入したのだが、従って夜毎に村人たちが語り手の家を訪れ、テレビの画面に釘付けになった。連日の賑わいに辟易した語り手は村人から「入場料」を取ることを思いつき、これが功を奏して、一家にはほどなく元通りの静かな暮らしが戻った。
私の家は富裕なわけではなかったが、親父がテレビを一早く購入した昭和30年代、近所の人たちが夜になると我が家にやって来て賑わったことを思い出した。
頭脳明晰な語り手は村を出て、町にある中学、高校を経て都会の大学に進学する。もちろん村ではただ一人の栄誉だ。だが、結果的に村を遠く離れることになり、家を継いで欲しいという両親の思いとは隔たった人生を歩むことになる。そして恋愛結婚。新婦の父親は政府の役人をしている有力者。結婚式には新郎の出身の村からは誰も招かれない。新婦は都会育ちのチベット人で「今や自分の母語もろくに話せない」。二人はやがてお互いに離婚を口にするようになる。冒頭の雪のシーンから二十数年経た今、語り手は都会の暮らしに倦み、幼馴染とも縁遠くなった故郷を懐かしく思い、都会では見ることのない雪を待ちわびる。
語り手が妻と口論する場面で次のような言葉がやり取りされる。「故郷の山と川はきれいだったなあ」「故郷、故郷って、そんなに故郷がいいなら、故郷に帰ればいいじゃない」「故郷ってものがない君が気の毒だよ」。著者とも親しい訳者の解説によると、この作品に描かれているのどかな田園風景は著者のチベットの故郷からもほとんどが既に失われてしまったという。著者の後書きを読むと、著者は(当時)三歳の息子のために、自分自身の故郷を舞台にした小説を書いておきたかったのだという。都会で生まれ、都会で育つ息子は自分の故郷のように懐かしむ場所も振り返る場所もないからだとか。
著者は「今は故郷を捨て去る時代である」とも後書きで憂えている。私も宮崎の山里に生まれ、自分なりに一生懸命に生きてきたつもりだが、ふと我に返り、足元を見回すと、過疎の故郷は「捨て去られ」つつある。世代も国も異なるが、故郷の喪失感は似たようなものらしい。『雪を待つ』を読みながら、幾度となく自分の来し方に思いを馳せた。
- Newer: 中国ははるか先を歩いていた!?
- Older: Trumpism(トランプ主義)?