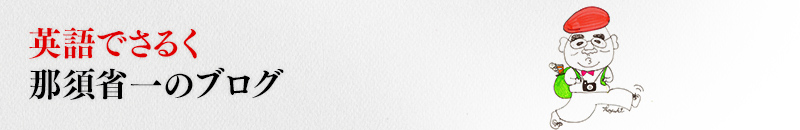- 2017-03-14 (Tue) 12:19
- 総合
帰省中に『マオ 誰も知らなかった毛沢東』(講談社)という翻訳書を読んだ。原著者は自伝的ノンフィクションの『ワイルド・スワン』で知られる中国人作家のユン・チアン氏と彼女の夫であるジョン・ハリデイ氏の二人。悪名高い文化大革命(1966-76年)での同胞に対して行った残忍非道な暴力事件の数々など、毛沢東という人物、その為政にいくばくかの憧れを抱いている読者は実像との「落差」に打ちのめされるに違いない。
この書では現代中国の建国の父とも言える毛沢東が権謀術数を労して権力の座に上り詰め、その後も政敵を卑劣に追い落とし、自分は酒池肉林の日々にありながら、国民には窮乏と飢餓の暮らしを強いていたことが淡々とした筆致で描かれている。彼の治世下で実に7000万有余の人々が平時において死に追いやられたと指弾されている。
読み進めるにつれ、「目から鱗」の書だった。日中戦争では毛沢東が率いる中国共産党軍は激しい抗日の戦いを繰り広げたと信じられているが、実情はその逆であり、彼はむしろライバルの蒋介石の国民党軍を日本軍が殲滅することを願い、そのような戦術に出たことが明らかにされている。また、彼は日中戦争にソ連の介入を強く望み、ソ連と日本が中国を分割するシナリオを頭に思い描いていた。そうなれば、ソ連の支援を受け、中国に共産党政権を樹立する道が容易に開かれると信じていたからだ。
軍事大国を目指す毛沢東は自分たちでは製造ができない武器を入手するためにも、同盟国のソ連にすり寄った。最終的にはソ連から原爆の製造に必要な施設の建設の確約を取り付けると、毛沢東は最高指導部のメンバーを前に次のように語ったという。「われわれは地球を支配しなければならない!」
毛沢東は文化大革命に先立つ大躍進政策(1858-61年)で重労働を伴う無謀な食糧供出計画を実施する一方、貧困にあえぐ農家から農機具、鍋釜など一切の鉄製品を徴収する馬鹿げた政策を実施し、多くの国民を死に追いやっている。次のように記されている。大躍進と大飢饉の四年間で、三八〇〇万人近い人々が餓死あるいは過労死した。これは二〇世紀最悪の飢饉、人類史上最悪の飢饉だった。毛沢東は計算ずくで何千万という人々を餓死や過労死へ追いやったのである。実際には、毛沢東はさらに多くの人間が死ぬことを計算に入れていた。最近になってようやく、毛沢東がどれほど多くの人命を失ってもかまわないと考えていたかを確実に知ることができるようになった。一九五七年にモスクワを訪問した際に、毛沢東は「われわれは世界革命に勝利するために三億の中国人を犠牲にする用意がある」と言った。当時の中国の全人口の半分である。(第40章 大躍進————国民の半数が死のうとも)
彼の独裁的手法に最後には反旗を翻した劉少奇、彭徳懐、林彪らの側近。彼らも次々に粛清されていったことが劇的に綴られている。西側では好意的に今なお受けとめられているあの周恩来首相が毛沢東の前では全くの腑抜けだったことも詳述されている。
この書はユン・チアン氏とハリデイ氏が十余年にわたる綿密な調査と数百人に及ぶ関係者へのインタビューの末に書き上げたものという。私が手にした単行本だと上下で一千ページを優に超える分量だ。英語版の刊行からすでに十年以上が経過しているが、中国の一般大衆が普通にこの本を手にして読むことはないのだろうか。(続あり)
印象に強く残った文章を以下に適宜端折りながら紹介しておきたい。
毛沢東がスターリンに何より期待していたのは、中国が世界の軍事大国となるための援助だった。そのために重要なのは、スターリンからいかに多くの兵器を援助してもらうかではなく、中国が自力で兵器を製造するための技術やインフラをスターリンからいかにして引き出すかであった。(第33章 二大巨頭の格闘 1949-50年)
農民から搾り取った貴重な農産物は、ソ連や東欧から軍事品を輸入する代価として使われただけでなく、国際的影響力の拡大をもくろむ毛沢東が各国に景気よくばらまく援助としても使われた。中国が食糧を贈った相手は、北朝鮮や北ベトナムのような貧しい国々に限らなかった。とくにスターリンの死後、毛沢東を世界共産主義陣営の頭目に据えることを目指した時期には、中国よりはるかに裕福なヨーロッパの共産主義諸国にも気前よく食糧を贈与した。一般の中国人は毛沢東の大盤振る舞いに対して何も発言できなかっただけでなく、そもそも自分の国がそのように気前よく食糧をばらまいている事実自体を知らなかった。(第36章 軍事超大国計画 1953-54年)
1966年5月末、毛沢東は文化大革命という名の大粛清を進める機関として新しく中央文化革命小組を設置した。毛沢東に代わって小組を率いるのは江青で・・・。当局のお墨付きを得た近衛兵は、市民の家に乱入して書物を焼き、書画を裂き、レコードや楽器を踏みつぶし、とにかく「文化」に関係するものを片っ端から破壊した。また、「貴重品」を没収し、持ち主をしこたま殴りつけた。近衛兵の襲撃を受けた人々の多くは、自宅で残虐行為を受けて死亡した。映画館や劇場やスポーツ施設を利用した間に合わせの拷問部屋へ連行されていった人々もいた。足音も猛々しく街路を闊歩する近衛兵、文化を焼き捨てる炎、犠牲者たちの絶叫————一九六六の夏は、こうした光景と音で人々の記憶に焼きついた。(第48章 文革という名の大粛清)