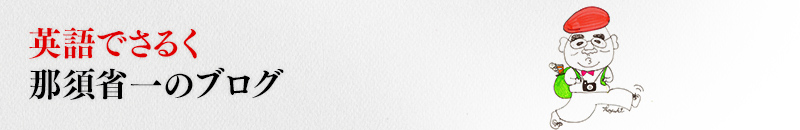- 2015-08-06 (Thu) 10:53
- 総合
先に大岡昇平の『野火』を読んだことを書いた。岩波文庫のその本には『ハムレット日記』も収められていた。父親である先王を叔父に毒殺され、母親の王妃をも奪われた王子ハムレットが復讐を果たして果てるシェイクスピアの悲劇『ハムレット』を下敷きにした作品だ。なるほど、こういう「料理」の仕方もあるのだと感心した。
実は少しく考えていることがある。とある文学作品(短編)を読ませて、余韻(複数の解釈の素地)のある結末部を学生に自由に拡大創作させる手法だ。読み手の読解力・文章力が問われることになる。『ハムレット日記』を読みながら、そのことを思い出した。
末尾の解説によると、大岡はこの作品をデンマークの王子ハムレットが王座を狙うマキャベリストとしての試練と没落を描く政治小説に仕立て上げたのだという。ハムレットは日記に以下のように綴っている。「今日のデンマークがあるのは、父上の永年の御苦心の結晶である。その王国を憎むべき弑逆によって奪われ、現に王座に座っている者が、殺人者とその共犯者であるとすれば、子としてこれが放っておけようか」
父親の敵討ちに冷めた部分もある。「古い土地にかじりついている貴族、フランス流の口舌の猿真似する廷臣、どら声の軍人、嘘吐きの坊主どもが、柄になくデンマークの宮廷の体裁を整えようとあくせくしている有様は、浅ましいというほかはない。かかる宮廷に王として臨むことに、どれだけの値打があるというのだ」「クリスマス、聖歌、正餐、新年の謁見、賀宴————(中略)人々は人生がどこまでもこのまま続くと確信したかのように、晴れやかに着飾り、その衣装と同じくらい晴れやかな顔付で、参列し、行進し、挨拶し、酒を飲み、肉を食った。儀式は生活の意味をしばらく見失わせる。しかし宴果てた後、再び始まる毎日の生活の惰性が、元と同じ流路しか見出せぬところに不幸がある」
確かに意欲的な作品だったが、私にはだいぶ前に読んだ福田恆存訳のストレートな『ハムレット』の方がより楽しめたように思えた。拙著『イギリス文学紀行』でも言及したが、父の無念、母の裏切りの前に苦悶するハムレットが次のように独白する場面が印象に残っている。「その気になれば、短剣の一突きで、いつでもこの世におさらば出来るではないか。それでも、この辛い人生の坂道を、不平たらたら、汗水たらしてのぼって行くのも、なんのことはない、ただ死後に一抹の不安が残ればこそ。旅だちしものの、一人としてもどってきたためしのない未知の世界、心の鈍るのも当然、見たこともない他国で知らぬ苦労をするよりは、慣れたこの世の煩いに、こづかれていたほうがまだましという気にもなろう・・・」
原作では失意のうちに夭折した恋人オフィーリアの墓穴を掘っている墓堀人と、英国に追放される寸前でデンマークに戻ってきたハムレットとの会話が読ませる。相手がハムレットと知らない墓堀人は、尋ねられるままに、ハムレットは狂気を癒すために英国に送られたが、向こうで快癒しなくても大丈夫、あそこにはそんな人間ばかりだとうそぶく。
大岡は墓堀人に次のような軽妙な歌を歌わせる。「王様が王冠(クラウン)をなくしたら、道化(クラウン)になんなさった。世も末だよ。王様が王冠をなくした。天地がひっくり返った。王様はおかわいそうに、道化になりなさった」。こういうくだりはさすがに原作にはない。王冠(crown)と道化(clown)の発音が似ているのを活用している。我々日本人にはその違いの聞き取りが悩ましい発音の語彙だ。