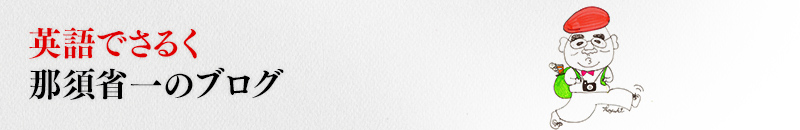- 2015-07-09 (Thu) 14:37
- 総合
今朝、近くのコンビニに宅急便を出しに出かける。エレベーターを降りた途端、ムッとする外気に当たってすぐに感じた。「おや、これはもう夏の空気だ。そうか、これから本格的夏の到来だな」と。まだ扇風機で何とか済ませているが、いよいよ冷房の出番か。
◇
短編小説の名手として知られるフランスの文豪ギィ・ド・モーパッサン(1850-1893)の代表作と言われる『女の一生』を読んだ。もちろん翻訳本だ。光文社という出版社から「古典新訳」と題した一冊が出ていた。永田千奈という方の訳本だった。全体に読みやすい現代文に訳されており、するすると読み進めることができた。恥ずかしいが、この作家の本を読むのは初めて。
2012年にイギリス文学の名作ゆかりの地を訪ねる旅にあった時、ロンドンの書店で購入したサマセット・モーム(1874-1965)の伝記本 “The Secret Lives of Somerset Maugham”でもモーパッサンのことが何回か出てきていた。
短編の名手として知られるモームが深い敬意の念を抱き、お手本とした作家がモーパッサンだったという。上記の伝記本からモームがモーパッサンのことを称えたそのくだりをそのまま引くと・・・ “I had at that time a great admiration for Guy de Maupassant … who had so great a gift for telling a story clearly, straightforwardly and effectively, …”(私は当時モーパッサンに深く敬服していた。彼は物語を明確にかつ分かりやすくそして効果的に語る一方ならぬ才能を有していた)
1883年に発表された『女の一生』は短編ではない。19世紀のフランス・ノルマンディ地方を舞台にした男爵家の娘で、文字通り世間知らずのお嬢様、ジャンヌがヒロインとなったお話だ。婿にもらった子爵の夫がとんでもない食わせ者で極めつけの吝嗇家である一方、女にも手が早く、あろうことか、男爵家を訪れたその夜にジャンヌの乳姉妹である女中(お手伝い)のロザリに手をつけるような男だ。当然その結婚がハッピーエンドになるわけはなく、ジャンヌは傷心の晩年(中年というべきか)を過ごすことになる。
不実の夫に先立たれ、愛する両親とも死別し、彼女が余生を頼むただ一人の存在、愛息も母親のジャンヌのことなど眼中になく、極めていい加減な人生を送っている(ように見える)。生きる意欲を失い、自分の不運の人生を嘆くジャンヌに対し、晩年は後見人となったようなロザリが次のように言って叱咤激励する場面が印象的だ。
「食べるものに困って働かなければならないわけでも、毎朝六時に起きて一日じゅう働くわけでもないのに、何をおっしゃいますか。そうでもしないと生きていけない人はたくさんいるんですよ。そういう人たちは一生働いた挙句に、年をとって働けなくなったら、惨めに死んでいくしかないんですからね」
モーパッサンはわずか40数年でこの世を去り、晩年は精神を病んでいたという。リアリズム文学の旗手であり、日本の文壇にも大きな影響を与えたと言われる。私はヒロインのジャンヌの栄枯盛衰よりも、物語の筋に何ら影響を及ぼすことなく、親類一同から一顧だにされず、ひっそりと物語の舞台から消えていったリゾン叔母の方が気になった。
- Newer: 「生きていることが愉しい」時代?
- Older: Thrashed!