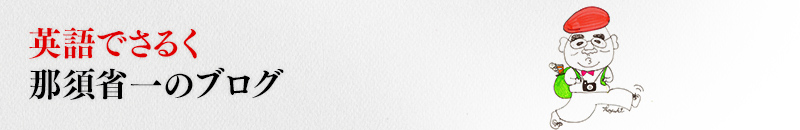- 2020-01-29 (Wed) 10:43
- 総合
 『シエラレオネの真実 父の物語、私の物語』(亜紀書房)というノンフィクションの作品を読んだ。原題は “The Devil that Danced on the Water: A Daughter’s Quest”。著者は西アフリカ、シエラレオネ人の父親とスコットランド人の母を持つ作家のアミナッタ・フォルナ氏。1964年生まれとあるから五十代半ばの女性だ。
『シエラレオネの真実 父の物語、私の物語』(亜紀書房)というノンフィクションの作品を読んだ。原題は “The Devil that Danced on the Water: A Daughter’s Quest”。著者は西アフリカ、シエラレオネ人の父親とスコットランド人の母を持つ作家のアミナッタ・フォルナ氏。1964年生まれとあるから五十代半ばの女性だ。
邦題が示す通り、1960-70年代のシエラレオネを主な舞台に、著者の父親で当時、財務大臣の要職にあったモハメド・フォルナ氏が独裁的なシアカ・スティーブンス大統領に疎まれ、国家転覆罪で絞首刑に処せられた経緯を知るために、著者が祖国を再訪し、関係者に取材、真相を追求していく物語。父親を失った娘としての喪失感とともにシエラレオネの恥辱的な現代史が明らかにされる。普通に読めば、頭脳明晰なモハメド氏がなぜ、狡猾で残忍な大統領の魔の手が迫って来る前につてのある英国に亡命しなかったのか、家族の大切さを第一義に考えなかったのかという疑念がわく。そうした機会は何回かあったのだ。
物語の冒頭は1974年7月30日。著者は10歳とある。シエラレオネの首都フリータウン。「言いようのない危険な雰囲気を感じさせる」二人の男がやってきて、私(アムナッタ)の父親をどこかに連れていく。「お母さんに遅くなると言いなさい」という言葉が耳にした父の最後の言葉だったとある。
物語の舞台はロンドンに跳ぶ。「父の死から25年が過ぎたにもかかわらず」父の夢を見なくなることはなかったと記されている。著者はロンドン大学で学び、ジャーナリストとなっている。著者は父親の逮捕後、兄や姉、義母とともにロンドンに逃れており、シエラレオネの記憶は薄れている。かすかに残っている記憶を基に父親の足跡をたどるのだが、祖国はまだ反政府軍との間で激しい内戦状態にあり、危険と隣り合わせの取材を続けていく。父親に対する深い愛慕の念がなせる業だろう。物語の中で反政府軍により両足首や腕を切断された無垢の住民が描かれ、その酷さに胸がつまった。それでも彼らは希望を捨てていない。
私はシエラレオネを訪れたことはない。アフリカ特派員時代、支局は東アフリカ・ケニアのナイロビにあった。アフリカの地図を見ると、東西アフリカはそうは遠くない印象だが、地球が一番出っ張ったところであり、見た目以上に距離がある。加えて東西を結ぶ航空路線は多くなく、決して近いという印象ではなかった。また、西アフリカはフランス語圏の国が多いことも英語しか解さない日本人記者には取材意欲を削がれた。シエラレオネは英語が公用語であるもののだ。
言い訳ではないが、私がナイロビ支局に勤務していた1980年代末、シエラレオネは比較的静かな情勢が続いていた。敢えて書くと、この本に登場する大統領のように国民の幸福を一顧だにしない独裁的指導者はアフリカでは当時も今も珍しくない。そうした邪悪な指導者を一掃すべく、国際社会の断固とした対応が求められている。
訳者は1985年から2004年まで国連児童基金(ユニセフ)広報官を務めた澤良世氏。惜しむらくは著者の回想と四半世紀後の再訪の場面などが交錯した記述が多く、原文では違和感なく読み進めることができるのだろうが、日本語ではかなり戸惑う場面が少なくなかった。登場人物一覧も冒頭に別記してあれば役に立ったことだろうと思われた。
- Newer: vegan(厳密な菜食主義者)
- Older: brand-new