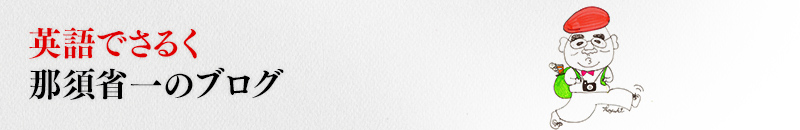- 2018-08-02 (Thu) 09:29
- 総合
7月30日は父親の命日だったことを思い出し、それを口実に焼酎のグラスを一人傾けた。親父が他界したのは私が大学に入学した年だった。50年近い歳月が流れている。
お袋の命日は忘れたことはないが、なぜか親父の命日はいつも「素通り」してきていた。今年は積年の親不孝を詫びて、焼酎のオンザロックを流し込んだ。大晦日に買った焼酎瓶に少し残りがあったのだ。なんのことはない、この猛暑で喉を潤したかっただけのことかも。
◇
お世話になっている出版社・書肆侃侃房からPRの小冊子「ほんのひとさじ」9号が刊行された。私も「踏切の向う」というタイトルで次の拙文を寄稿させてもらった。
◇
窓という言葉を聞いたら、ふつつか者の私は「社会の窓」という語が頭に浮かぶ。英語なら “social window” と訳したい衝動に駆られるが、これはもちろん通じない。「社会の窓が開いていますよ」と注意したければ、“Your fly is open.” と言えば十分だ。とまあ、そんな他愛ない話はいいとして、窓という言葉を聞いて、連想する文学作品を挙げよと言われたら、私は芥川龍之介の小品『蜜柑』を挙げるだろう。
「ある曇った冬の日暮である」という書き出しで始まる短編。横須賀線の列車内。「私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落していた」とある。精神を病み、昭和2年に35歳の若さで自死を選択した天才作家の末路が、読者にはすぐに想起される。「私」が乗る二等客車に「いかにも田舎者らしい娘」が慌ただしく駆け込んで来る。「私」の前の座席に坐した娘は三等の切符しか手にしていない。「私」は「この小娘の下品な顔だち」が気に入らず、「彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった」と続く。
「私」は窓枠に頭をもたせ、娘の存在を絶えず意識しながら、「不可解な、下等な、退屈な人生の象徴」に気が滅入り、うつらうつらし始める。ふと気づくと、汽車がトンネルに差しかかる直前、娘は何と汽車の窓を開けようとしている。悪戦苦闘の末に窓が開き、「私」は流れ込んで来る「煤を溶かしたようなどす黒い空気」にむせび苦悶する。憤懣やるかたない「私」がその直後に目にしたのは、トンネルを抜けた「貧しい町はずれの踏切」の柵の向こうに、「揃って背が低い」「頬の赤い三人の男の子」が佇んでいる光景だ。彼らは汽車に向かい一斉に歓声を上げる。窓から半身を乗り出した娘はそれまで懐に抱いていた「暖かな日の色に染まっている蜜柑」を男の子たちに五つ六つと投げ込む。「奉公先へ赴く」途中の娘は、「見送りにきた弟たちの労」に蜜柑で報いていたのだ。
「朗らかな心もち」に充たされた「私」は「言いようのない疲労と倦怠とを、そうしてまた不可解な、下等な、退屈な人生をわずかに忘れることができたのである」と結ばれている。
私にも姉がいた。高校時代には一緒に借家に住まい、一切の世話をしてくれた。母親や兄弟のために生きた人生だった。晩年は長いこと病床にあり、先日黄泉の国に旅立った。姉に一度でも感謝の言葉をかけたことがあっただろうかと悔いる。踏切の向こうで歓声を上げた『蜜柑』の弟たちに比べるべくもない。
- Newer: 「シュウキンペイ」って俺のことかい?
- Older: It's very hot every day.