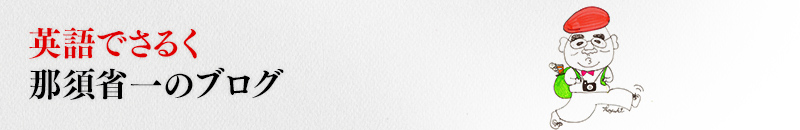- 2015-07-26 (Sun) 20:25
- 総合
滅多にならない玄関の呼び鈴がピンポン。大家さんだった。家庭菜園の野菜はいかがとの訪問だった。今回はミョウガにナス、トマトなど。「これはどう。美味しくて栄養がありますよ」と渡されたのが、ムラサキという葉っぱもの。熱湯でさっとゆでて、ポン酢で食べるとの由。早速教えられた通りにやってみる。なるほど、さっぱりして美味い。しまった。遠慮せずにもっともらっておけば良かった! 齢を重ねて知る野菜の有難さだ。
◇
芥川龍之介(1892-1927)の文庫本(集英社文庫)を買った。現代風の表紙になっており、『地獄変』や『羅生門』ほか短編が幾つか収められていた。
室町から戦国時代にかけての史実に材を取った『奉教人の死』は良かった。作家の心境を綴ったと思われる『蜜柑』も良かった。『蜜柑』の冒頭に「私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落していた」とある。精神を病み、昭和2年に35歳の若さで自死を選んだ作家の人生に思いを馳せざるを得ない。
その「私」が乗り込んだ二等客車の前の座席に駆け込んできたのは、三等の切符しか手にしていない「いかにも田舎者らしい娘」だった。「私」は「この小娘の下品な顔だちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった」とけんもほろろの書きようである。「私」はトンネルを通って走っていく汽車の座席に身を委ね、小娘の存在を絶えず意識しながら、「不可解な、下等な、退屈な人生の象徴」を思い、うつらうつらしていく。ふと気がつくと、娘は不可解にも汽車の窓を開けようとしている。トンネルに差しかかったところで窓が開き、「私」は流れ込んで来る「煤を溶かしたようなどす黒い空気」にむせび苦悶する。憤懣やるかたない「私」がその直後に目にしたのは、トンネルを抜けた「貧しい町はずれの踏切」の柵の向こうに、「揃って背が低い」「頬の赤い三人の男の子」が佇んでいる光景だ。彼らは汽車に向い一斉に歓声を上げる。窓から半身を乗り出した娘はそれまで懐に抱いていた「暖かな日の色に染まっている蜜柑」を男の子たちに五つ六つと投げ込んだ。「奉公先へ赴く」途中の小娘は、見送りに来ていた弟たちの労に蜜柑で報いたのだ。「私」は「ある得体の知れない朗らかな心もちが湧き上がってくるのを意識した」とある。
読者の私もほっとした。私は「奉公」という語感を辛うじて理解できる世代だろうか。思うに、昭和の繁栄はこういう小娘とその弟たちが担ったのだろう。
『秋』は数年前にアメリカかイギリスを旅している時、携帯していた電子辞書に収蔵されており、それで読んだことがある。独特の文体が印象に残っていた。次のような文章だ。「彼女は・・・我知れず耳を傾けている彼女自身を見出しがちである」。「夫は夜寒の長火鉢の向うに、いつも晴れ晴れと微笑している彼女の顔を見出した」。「彼女はふと気がつくと、いつも好い加減な返事ばかりしている彼女自身がそこにあった」。英語だと I found myself …. She found her …という構文の文章が頭に浮かぶ。
「瑣末な家庭の経済の話に時間を殺すことを覚えだした」という文章もあった。「時間を殺す」は英語のkill time の直訳だろう。作家は英語やフランス語に明るかった印象がある。自然と英仏語の表現を自分の文章に取り込み、活かしていったのだろうと推察される。
- Newer: 『文章読本』
- Older: “Go Set a Watchman”