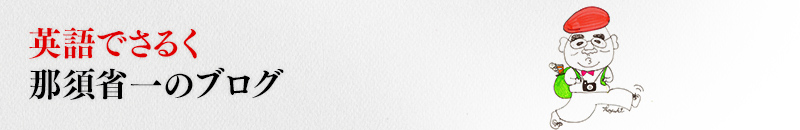- 2022-07-04 (Mon) 13:04
- 総合
 お世話になっている出版社からある詩人を紹介した英文のインタビュー記事を適宜要約してくれないかと依頼された。今夏に出す短歌誌に掲載する予定だとか。私には荷が重いと思ったが、インタビュー自体は大変興味深かった。出版されたばかりのその詩人の全集を送って頂き、詩人が手がけた英語短篇小説の翻訳や散文を読んで圧倒された。
お世話になっている出版社からある詩人を紹介した英文のインタビュー記事を適宜要約してくれないかと依頼された。今夏に出す短歌誌に掲載する予定だとか。私には荷が重いと思ったが、インタビュー自体は大変興味深かった。出版されたばかりのその詩人の全集を送って頂き、詩人が手がけた英語短篇小説の翻訳や散文を読んで圧倒された。
左川ちか。今の日本では無名の人だろう。1911年に北海道に生まれ、10代で翻訳家としてデビュー、翻訳家としても才覚を発揮し、将来を嘱望されていたが、病魔に襲われ、1936年24歳の若さで他界している。出版社から今回の依頼がなかったならば、私などはおそらく一生、この女流詩人の名さえ知ることはなかっただろう。
全集を読み進め、彼女が手がけた短篇小説の翻訳に驚かされた。英国でほぼ同じ時代を生きた作家、ヴァージニア・ウルフ(1882-1941)の作品を翻訳していた。英語では “A Haunted House” というタイトルで『憑かれた家』と訳されていた。ウルフは今も人気ある作家で20世紀モダニズムを代表する作家の一人だ。
“A Haunted House” は短い小品だが、これをすっと読み進めるのは、我々英語のノンネイティブにはそう簡単ではないかと思う。翻って左川は特に高い教育を受けた女性ではなかった。作家の伊藤整の知遇を得て周囲には当時のモダニズム運動に傾倒した文芸人たちがいたとはいえ、遠く離れた異国の言語を習得するのは並大抵のことではなかっただろう。パソコンやインターネット、スマホなどの電子機器とは無縁の時代だ。
そのことを考え、改めて彼女のウルフの翻訳を読むと、彼女の言葉の感性に敬服せざるを得ない。書き出しから素晴らしい。英文は次のように始まる。Whatever hour you woke there was a door shutting. From room to room they went, hand in hand, lifting here, opening there, making sure – a ghostly couple. 左川の訳は・・・眼が醒めてゐる時はいつも戸のしまる音がした。部屋から部屋へと彼等は行つた。手を取り合つて、ここのカーテンを掲げ、そこの扉を開けて。たしかに確信させながらーー幽霊の夫婦を。
「春・色・散歩」と題した散文は「遠くの空が黄色く光つて、目を細くしてゐるとそれが淡紅色の中に溶けてしまひ段々大きな拡がりになつて真白に輝いて来ると目を開いてゐることが出来なくなります」と始まる。「私は家の中にぢつとしてゐることが出来なくなり」船に乗ってどこかに旅することを夢想したり、疾走する自動車から振り落とされるスリルを想起したりする。「風景でも音響でもたえず動いてゐるものに魅力」を感じる私は、「郊外電車からバスに揺られて小さく刻まれて」視界に飛び込んでくる「街の絵は非常にヴイヴツトなものだ」と思うと綴られている。
「ヴイヴツト」は英語の “vivid”(生き生きとした)を拝借したのだろう。「ビビッド」とせずに実際の音を忠実に写し取っている。ほぼ100年前に生きたこの詩人・翻訳家が普通に長生きしていたら、どのような秀作を残していたことだろうと思わざるを得ない。
私は2012年に英国を旅した際にウルフが暮らした地を訪れ、記念館のようになっている、彼女が入水自殺するまで住んだ家にも足を運んだ。左川には望むべくもない贅沢な旅だった、とここで記しても何の意味もないことだが・・・。
- Newer: 自らを鼓舞するメッセージ?
- Older: (個人的)海開き