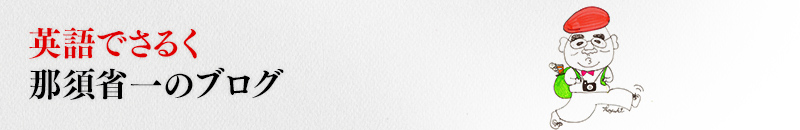- 2022-05-15 (Sun) 18:17
- 総合
 手元にあることを忘れていた、というか全く頭になかった英小説 “The Men and the Girls” は読み始めると面白く、数日で読み終えてしまった。Joanna Trollopeという作家の手になる300頁程度の中編小説。私は本当になぜこの本を購入したのか分からない。ひょっとしたら似たような名前の作家の作品と勘違いして洋書コーナーで買い求めたのかもしれない。時々難解な語彙が出てきて、その都度辞書を引く手間を余儀なくされた。辞書を引いてその意味を納得したが、おそらく大半はもう忘れているかもしれない。
手元にあることを忘れていた、というか全く頭になかった英小説 “The Men and the Girls” は読み始めると面白く、数日で読み終えてしまった。Joanna Trollopeという作家の手になる300頁程度の中編小説。私は本当になぜこの本を購入したのか分からない。ひょっとしたら似たような名前の作家の作品と勘違いして洋書コーナーで買い求めたのかもしれない。時々難解な語彙が出てきて、その都度辞書を引く手間を余儀なくされた。辞書を引いてその意味を納得したが、おそらく大半はもう忘れているかもしれない。
情けなく思うが、これはいかんともし難いことであろう。中国語の語彙でもNHKラジオの講座で何度も目にし、耳にした語彙もその漢字(簡体字)、ピンイン表記、声調を正確に記憶しているのは極めて難しい。例えば「災害」という語。中国語ではザイハイとか何とか呼ぶことは何となく頭に残っているが、これが「灾害」と簡体字で書き、zāihàiというピンイン表記となることは何度覚え(ようとし)てもすぐに忘れてしまう。
とまあそんなぼやきはともかく、“The Men and the Girls” は1992年にロンドンで刊行されている。私が新聞社の支局員としてロンドンに勤務していた頃とほぼ重なる。ともに30代半ばのKate とJuliaの二人の女性、彼女たちの60代前半の伴侶JamesとHughが登場する。テーマは女性の自立を求める心、束縛からの解放を願う心だろうか。
自分の才能を活かすメディアの仕事を満喫することを夫に受諾させたJuliaは、年齢的なこともありMCの仕事の契約を打ち切られ、やけになって家を捨てた夫のHughが反省して戻って来ることを許す。Kate はパートナーのJames、Jamesのさらに高齢の気の難しい叔父のLeonardと同居するようになって8年が経過。彼女には多感な14歳の娘が一人おり、この子育てにも四苦八苦する。さまざまなプレッシャーに押しつぶされた彼女は自ら家を出て、自由な身となる道を選ぶ。ただ一人の生きがいである娘はなぜか、何の血縁関係もないJamesや Leonardとの暮らしを選択する。Kateは新しい恋人に出会うが、心が満たされることはなく、最後にはJamesの元に戻り、それまで頑なに拒否していたJamesとの結婚を自ら求める。ハッピーエンドの結末は出来過ぎと思わないでもないが、就寝時に飽きることなく頁を繰り続けた。
この小説を読んでいて思わず笑ってしまったことがある。おそらくこの作家の日本人に対するイメージがこうした描写を盛り込ませたのだろう。Kateがイタリアンレストランでのウエイトレスの仕事からくたびれ果てて帰宅したシーンの描写だ。… it had been a non-stop day with the restaurant full of tourists, including what seemed like half a busload of Japanese who all ordered exactly the same thing which put Benjie in a temper.
Benjieとはレストランで働くシェフのこと。大挙してお店にやって来た日本人の団体客が同じ料理を注文したことに腹を立てたとか。イタリアンだからパスタでも注文したのだろうか。それも同じ種類のパスタを。シェフの腕前を振るうことができず、憤慨でもしたのだろう。私は80,90年代に日本人の「個性」がいや、「個性」のなさが海外でどう受けとめられていたかを垣間見るような気がした。私もその一人だったかもしれない。今はこのような記述がたとえ小説のたわいないワンシーンだとしても挿入されないように願う!